丂
丂
丂嬥懏傪揔摉側壏搙偵壛擬偟丆偦偺壏搙偵揔摉帪娫曐帩偟偰屻丄彊椻偡傞張棟傪從側傑偟乮annealing乯偲偄偆丏晛捠偼丄嵽椏傪楩偺拞偵擖傟偨傑傑丄楩偺揹尮傪愗傞丅楩偑椻媝偡傞偺偲摨偠懍搙偱椻媝偡傞丄偄傢備傞楩椻偱偁傞丅楩偺梕検偵傕傛傞偑60亷乛hr掱搙偺椻媝懍搙丅
丂
丂峾夠傑偨偼峾嵽拞偵懚嵼偡傞奺庬偺曃愅(嵽椏拞偺慻怐傗擹搙偺傓傜)傪彍嫀傑偨偼寉尭偡傞偨傔偵峴側傢傟傞從側傑偟傪奼嶶從側傑偟乮diffusion annealing乯偲偄偆丅壛擬壏搙偼崅偄傎偳丆帪娫傎挿偄傎偳岠壥偑戝偒偄丅偟偐偟崅壏搙偱挿帪娫壛擬偡傞偲僆乕僗僥僫僀僩兞偺寢徎棻偑慹戝壔偡傞偺偱從側傑偟偟偨屻丄從側傜偟側偳偺曽朄偵傛偭偰棻偺旝棻壔傪偡傞丅
丂
丂嬥懏嵽椏偼庬乆偺棟桼偱撪晹墳椡丄傂偢傒傪惗偠偰偄傞偙偲偑懡偄丅椺偊偽丄嵽椏帋尡偺帋尡曅傪嶌傞偲偒慁斦偱嶍傟偽丄昞柺憌偼慪惈曄宍偡傞偺偱巆棷傂偢傒偑懚嵼偡傞丅偙傟偼丄慪惈曄宍偵傛傝丄戝検偺揮埵偑敪惗偟丄偦偺傑傑巆傞偙偲偐傜惗偢傞丅擬張棟偟側偄偱旀楯帋尡傪偡傞偲偙偺塭嬁傪庴偗傞丅
丂
丂傑偨丄偙偺傛偆側撪晹墳椡丄傂偢傒偑偁傞嵽椏傪愗嶍壛岺偟偨傝丆挿帪娫巊梡偟偰偄偨傝偡傞偲嫸偄傪惗偢傞丅巆棷墳椡傪彍偔偨傔偵嵽椏傪備偭偔傝壛擬偟偰丄偦偺壏搙偵堦掕帪娫曐帩偟丄偦偺屻丄椻媝拞偵傕巆棷墳椡傪惗偠側偄傛偆偵備傞傗偐偵椻媝偡傞偙偲傪傂偡傒庢傝從側傑偟乮stress relieving annealing乯偲偄偆丅壛岺偝傟偨庬乆偺嵽椏帋尡偺帋尡曅偼昁偢偙偺擬張棟傪峴偆丅
丂傂偢傒庢傝從側傑偟偼丆夞暅丆嵞寢徎傪婲偙偝偣傞偙偲偱偁傞丅巆棷墳椡偼嵽椏傪嵞寢徎壏搙埲忋偵壛擬偡傟偽揮埵偑徚柵偟丄怴偟偄柍傂偢傒偺嵞寢徎棻偑偱偒傞偙偲偵傛傝傎偲傫偳徚幐偡傞丅弮揝偺嵞寢徎壏搙偼350乣450亷偱偁傞偐傜峾偺傂偢傒庢傝從側傑偟偼丄450乣600亷丄1帪娫敿曐帩掱搙偱峴側傢傟傞丅
丂偦偺懠丄巆棷墳椡偼丆拻憿丄椻娫壛岺丄抌憿丆梟愙丆從擖傟丆愗嶍側偳偵傛偭偰傕惗偢傞丅
丂峝偔丄愗嶍壛岺傗慪惈壛岺傪偟偵偔偄嵽椏傪擃壔偝偣偰壛岺傪梕堈偵偡傞偨傔偵峴側傢傟傞從側傑偟擬張棟傪擃壔從側傑偟乮softening丂annealing乯偲偄偆丅偦偺栚揑傪払偡傞偙偲偑偱偒傟偽丆偳偺傛偆側曽朄傪偲偭偰傕傛偄丅傕偟傕丆偦偺嵽椏偑椻娫壛岺偵傛偭偰峝壔偟偰偄傞傕偺側傜偽丆夞暅(壛岺慜偺忬懺偵栠傞尭彮)傗嵞寢徎傪婲偙偝偣傟偽椙偔丆從擖傟偵傛偭偰峝偔側偭偰偄傞傕偺側傜偽丆晛捠傛傝傕崅偄壏搙偱從傕偳偟傪偡傞丅
丂
丂偄傑傑偱偺愢柧偵傛傞偲丆垷嫟愅峾(扽慺検<0.8%)偼僼僃儔僀僩偲憌忬僷乕儔僀僩丆嫟愅峾(扽慺検=0.8%)傎憌忬僷乕儔僀僩偺傒丆傑偨夁嫟愅峾(扽慺検>0.8%)側傜偽栐栚忬偺弶愅僙儊儞僞僀僩偲憌忬僷乕儔僀僩偲偐傜惉傝棫偭偰偄傞丅偙傟傜偵懳偟摿暿側從側傑偟傪峴側偆偲丆僙儊儞僞僀僩傎媴忬偲側傝丆抧偼僼僃儔僀僩偵側傞丅偙偺從側傑偟傪媴忬壔從側傑偟偲偄偆丅傑偨偙偺傛偆側慻怐傪媴乮棻乯忬僙儊儞僞僀僩丆傑偨偼媴忬僷乕儔僀僩乮spheroidite丄spheroidal丂pearlite,globular cementite乯偲偄偆丅憌忬僷乕儔僀僩偵斾傋丆摨偠扽慺検偺傕偺偱傕擃偐偔丆愗嶍壛岺丆慪惈壛岺偑梕堈偱偁傞丅憌忬僷乕儔僀僩偼丄斾妑揑廮傜偐偄僼僃儔僀僩偲峝偄僙儊儞僞僀僩偑岎屳偵憌忬傪側偟丄暋崌嵽偺傛偆偵嫮搙偑偁傝擲傝嫮偝傕桳偡傞丅
丂幉庴峾傗岺嬶峾側偳偱偼媴忬壔從側傑偟傪偡傞丅
丂
| (1) | Ac1捈壓偺600乣700亷偵壛擬偟丄曐帩丅娙扨偵媴忬壔 |
| (2) | A1埲忋偺壛擬丄曐帩屻丄A1捈壓偺壏搙偵曐帩偙傟傪傕偆堦搙孞傝曉偡丅 丂丂栐栚忬僙儊儞僞僀僩偺堦晹偑兞拞偵梟偗崬傒丆椻媝拞偍傛傃A1捈壓偺壏搙偵曐帩偡傞娫偵媴忬壔偑峴側傢傟傞丅 |
| (3) | 嬒堦側僆乕僗僥僫僀僩兞偺椞堟傑偱壛擬偟偰丄扽慺尨巕C傪堦條偵暘晍偝偣丆偦傟偐傜弶愅僙儊儞僞僀僩傗嫟愜僙儊儞僞僀僩偑戝偒偔弌側偄傛偆偵媫懍側椻媝乮從擖傟側偳乯傪偟偰丆偦偺屻丅乮1乯傑偨偼乮2乯偺曽朄偱從側傑偟傪偡傞丅 丂 |
丂椻娫壛岺傑偨偼從擖傟側偳偺塭嬁傪姰慡偵側偔偡偨傔偵丆嬒堦僆乕僗僥僫僀僩偺椞堟傑偱壛擬偟丆偙傟傪彊椻偡傞偙偲傪姰慡從側傑偟乮full annealing乯偲偄偆丅壛擬壏搙偑崅偗傟偽丆惉暘偺嬒堦壔傕偁傞掱搙偼峴側傢傟丆廫暘偵彊椻偡傟偽撪晹墳椡傕彍嫀偝傟丆嵽椏偼廫暘偵擃壔偝傟傞丅姰慡從側傑偟傪偟偨傕偺偺慻怐偼僼僃儔僀僩偲憌忬僷乕儔僀僩丆憌忬僷乕儔僀僩偲弶愅僙儊儞僞僀僩偱偁傞丅偨偩扨偵從側傑偟偲偄偆応崌偵傎姰慡從側傑偟傪堄枴偡傞偙偲偑懡偄丅
丂
丂
丂偁傜偄慻怐偺垷嫟愅峾(扽慺検<0.8%)傪壛擬偡傞偲偒偺曄壔傪峫偊偰傒傞偆丅A1揰傑偱偼曄壔偼婲偙傜側偄偑丆A1揰偵払偡傞偲僆乕僗僥僫僀僩兞偺彫棻偑僼僃儔僀僩兛偲僙儊儞僞僀僩Fe3C偲偺嫬奅偺晹暘偵乮兛偼掅C検偱丆Fe3C偼崅C検偱偁傝丆兞偼偦偺娫偺C検偱偁傞偐傜乯柍悢偵尰傢傟傞丅A1偺曄壔偍傛傄A1仺A3偺壛擬拞偵偦偺悢偲戝偒偝偲傪彊乆偵憹偟丆A3揰偵払偟偨偲偒偵偼慡晹偺慻怐偑嵶偐側僆乕僗僥僫僀僩兞偲側傞丅兛丆兞偺嬫暿傪偟側偄偱偨偩寢徎棻偺戝偒偝偲偄偆棫応偱峫偊傟偽丆慻怐偺偁傜偄峾傪A1丆A3傪捠夁偝偣偰壛擬偡傞偲峾偼婮嵶壔偝傟傞偲偄偆偙偲偑偱偒傞丅
丂A3揰傪墇偊偰偝傜偵壏搙傪忋偘傞偲兞棻偼媫懍偵戝偒偔側傞丅戝棻偺兞偑彫棻偺兞傪庢傝崬傒丄惉挿偡傞偨傔偱偁傞丅偙偺尰徾傪僆乕僗僥僫僀僩兞棻偺慹戝壔乮grain丂glowth乯偲偄偆丅慹戝壔偟偨兞傪椻媝偡傞偲幒壏偵偍偗傞慻怐傕偁傜偔側傝丆嫮搙傕掅壓偟丄嵶偐側兞傪椻媝偡傞偲慻怐偼嵶偐偔側傝丄嫮搙傕忋偑傞丅傑偨兞忬懺偐傜偺椻媝懍搙偑抶偄偲偁傜偔側傝丆椻媝懍搙偑戝偒偄偲嵶偐偔側傞丅
丂峾傪僆乕僗僥僫僀僩兞壔偟丆兞棻偑偁傜偔側傜側偄偆偪偵媫椻乮儅儖僥儞僒僀僩壔偟側偄掱搙丆晛捠偼嬻椻乯偡傞偲丆幒壏慻怐偑嵶偐偔側傞丅偙偺憖嶌傪從側傜偟傑偨偼從弨乮normalizing乯偲偄偆丅楩偐傜僆乕僗僥僫僀僩偺帋椏傪庢傝偩偟丄嬻婥拞偵曻抲偟偰偍偔嬻椻丅
丂堎忢偵偁傜偔側偭偰偄傞慻怐傑偨偼從擖傟側偳傪峴側偭偨慻怐側偳傪丆惓忢側慻怐丆偮傑傝丄慹偔側偄僼僃儔僀僩偲僷亅儔僀僩偺慻幆偵曄偊傞偲偄偆堄枴偱偡丅
丂
丂
丂峾傪僆乕僗僥僫僀僩兞偑懚嵼偡傞椞堟傑偱壛擬偟丄偙偺壏搙偱偁傞帪娫曐帩屻丄悈偺拞偵擖傟偰媫椻偡傞擬張棟偱偁傞丅
丂峾傪從擖傟偡傞応崌丆從擖傟偵傛偭偰廫暘側峝偝偵側傞偙偲丆昁梫側怺偝傑偱峝壔偡傞偙偲偑栚揑偱丆從妱傟傗嬌抂側從嬋傝乮從傂偢傒乯傪惗偠側偄偙偲丆巁壔傗扙扽傪婲偙偟偦偺偨傔偵峾偺惈幙傪偦偙側傢側偄偙偲側偳偱偁傞丅從擖傟偨峾偼偦偺傑傑梡偄傜傟傞偙偲偼側偔丆昁偢乮摿庩側応崌傪彍偒乯從傕偳偟偟偰偐傜巊梡偝傟傞丅
丂
丂峾傪僆乕僗僥僫僀僩兞偑懚嵼偡傞椞堟傑偱壛擬偡傞丅晛捠偼垷嫟愅峾側傜偽A3慄埲忋30乣50亷丆嫟愅帞偍傛傃夁嫟愅峾側傜偽A1埲忋30乣50亷偑揔摉側壛擬壏搙偲偝傟偰偄傞丅傕偟傕垷嫟愅峾傪A3乣A1偺娫偺壏搙偐傜從擖傟傪偡傞偲丆偦偺壏搙偱懚嵼偡傞兞偼儅儖僠儞僒僀僩壔偝傟傞偑丆僼僃儔僀僩偼峝壔偟側偄偺偱丆從擖傟偨慻怐偼峝偄儅儖僥儞僒僀僩偲擃偐偄僼僃儔僀僩偲偺崿崌慻怐偲側傞丅
丂壛擬壏搙偑崅偡偓傞偲丆兞偺寢徎棻偑慹戝壔偟丆惗惉偝傟傞儅儖僠僜僒僀僩慻怐偼丆偦偺偨傔丆偁傜偔側傝丆從傕偳偟屻偺擲傝嫮偝偑楎傞偙偲偵側傞丅夁嫟愅峾偺壛擬壏搙偑崅偡偓傞偲丆忬懺恾偐傜柧傜偐側傛偆偵兞偺扽慺擹搙偑崅偔側傝丆偐側傝偺検偺兞偑儅儖僠僜僒僀僩偵側傜偢偵幒壏偵払偡傞丅偙偺兞傪巆棷僆亅僗僥僫僀僩乮retained austenite乯偲偄偆丅巆棷兞偑懡検偵偱偒傞偲從擖峝偝偼廫暘偵忋傜偢丆傑偨屻偱弎傋傞傛偆側懡偔偺奞傪媦傏偡丅傑偨從擖壏搙偑崅偡偓傞応崌偵偼丆壛擬拞偵巁壔傗扙扽偑婲偙傝丆峾偵偲偭偰戝愗側崌嬥尦慺偱偁傞扽慺C偑幐傢傟傞壜擻惈偑偁傞丅
丂峾傪從擖傟傞偲偒偺壛擬壏搙偲偟偰偼丄椺偊偽丄0.37亾C偺扽慺峾偱偼850亷偔傜偄丆0.85亾C偺峾偱偼780亷偔傜偄偑嵟揔壛擬壏搙偱偁傞丅
丂
丂從擖壛擬偡傞慜偺峾偼僼僃儔僀僩偲僷乕儔僀僩丆僷乕儔僀僩偺傒傑偨偼僷乕儔僀僩偲弶愅僙儊儞僞僀僩偱偁傞丅偙傟傪壛擬偟偰垷嫟愅峾側傜偽嬒堦扽慺擹搙傪帩偭偨僆亅僗僥僫僀僩兞偵丆傑偨夁嫟愅峾側傜偽媴忬偺僙儊儞僞僀僩偲僆亅僗僥僫僀僩兞偲偵偟偰傗傞偺偑從擖壛擬偺栚揑偱偁傞丅
丂幒壏偵偍偗傞扽慺擹搙偼丄僼僃儔僀僩偼旕忢偵掅偔乮嫟愅壏搙偱傕傢偢偐0.02亾偱偁傞乯丆懠曽丄僙儊儞僞僀僩偼旕忢偵崅偄乮6.67亾乯丅偙偺僼僃儔僀僩偲僙儊儞僞僀僩偲偑壛擬偵傛偭偰丆嬒堦扽慺擹搙傪傕偭偨兞偵側傞偨傔偵偼C尨巕偺堏摦偺偨傔偺帪娫偑昁梫偱偁傞丅傑偨戝宍偺嵽椏偱偼拞怱晹偑偦偺壏搙偵側傞偨傔偺帪娫傕偐側傝昁梫偱偁傞丅壛擬帪娫偑抁偄偲丆僙儊儞僞僀僩偑巆傝丆傑偨廫暘偵兞偑惗惉偝傟側偄偙偲偑偁傞丅堦曽丄壛擬帪娫偑挿偡偓傞偲丄壏搙偑崅偡偓傞偺偲摨條偵巁壔傗扙扽丆兞棻偺慹戝壔側偳偑婲偙傞丅
丂
丂從擖傟偨峾傪嘳慄偱挷傋偰傒傞偲丆僆乕僗僥僫僀僩兞偼100亾儅儖僥儞僒僀僩偵曄傢傞偺偱偼側偔丆扽慺峾偱偼悢亾乣30亾偔傜偄偼儅儖僠僜僒僀僩偵曄壔偟側偄偱丆僆乕僗僥僫僀僩兞偺傑傑偱幒壏偵払偡傞丅偙傟偑巆棷僆乕僗僥僫僀僩乮retained丂austenite乯偱偁傞丅
丂恾1偼兞壔偟偨峾傪悈椻偟丆堷懕偄偰幒壏埲壓傑偱椻媝偟偨応崌偺挿偝偺曄壔傪帵偟偨傕偺偱偁傞丅儅儖僥儞僒僀僩偵曄傢傞偨傔偺朿挘偼Ms揰偱巒傑傞偑丆幒壏傑偱椻媝偟偨偲偙傠偱廔傞偺偱偼側偔丆幒壏埲壓傑偱懕偒丆偙偺曄壔偑廔傟偽廂弅偵堏傞丅偙偺壏搙傪Mf揰乮martensite finish偺堄枴乯偲偄偆丅偙偺傛偆偵丆從擖傟偟偨峾傪幒壏埲壓偺壏搙傑偱椻媝偟丆巆棷僆乕僗僥僫僀僩傪儅儖僥僜僒僀僩偵曄偊傞張棟傪怺椻張棟乮sub亅Zero treatment乯偲傛傉丅怺椻張棟偵傎僪儔僀傾僀僗乮亅78亷乯丆塼媥拏慺乮亅195亷乯丆椻搥婡乮亅80亷偔傜偄乯側偳偑梡偄傜傟傞丅
丂巆棷兞偑懡検偵惗偢傞偲丆從擖峝偝偼廫暘偵忋傜側偄丅傑偨偙偺兞偼幒壏偱傎晄埨掕側憡偱偁傞偐傜丆挿帪娫巊梡偡傞娫偵埨掕壔傊偺曄壔偑恑傒丆偦偺偨傔偺悺朄曄壔傪婲偙偡乮宱擭曄宍偲偄偆乯丅傑偨丄尋杸偺偝偄偵儅儖僥儞僒僀僩壔偑婲偙傝丆偦偺偨傔偵妱傟傪惗偢傞偙偲偑偁傞乮尋杸妱傟偲偄偆乯丅
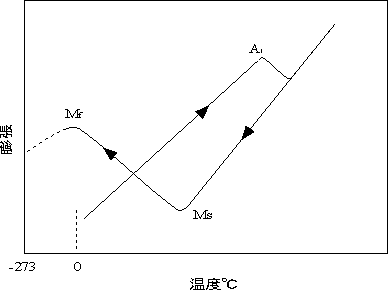
恾侾丂嫟愅峾(0.8%C)偺從偒擖傟帪偺挿偝偺曄壔丄悈從偒擖傟丄
Ms:儅儖僥儞僒僀僩曄懺奐巒
Mf:儅儖僥儞僒僀僩曄懺廔椆
丂
丂峾傪從擖傟偡傞偙偲偵傛偭偰摼傜傟傞嵟崅偺峝偝乮儅儖僥儞僒僀僩偺峝偝乯偼丆屌梟扽慺C検偵傛偭偰堎側傞丅恾俀偼偙偺娭學傪帵偟偨傕偺偱偁傞丅C検偑0.6亾傑偱偼C検偺憹壛偲偲傕偵從擖峝偝偑崅偔側傞偑丆偙傟埲忋C検偑憹偟偰傕HRC65埲忋偵偼側傜側偄偙偲偑傢偐傞丅
丂
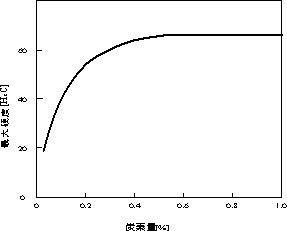
恾俀丂從偒擖傟峝偝偲扽慺峾偺扽慺検偺娭學
丂峾傪儅儖僥僜僒僀僩偵曄壔偝偣傞偨傔偵偼丆傑偢偙傟傪壛擬偟偰兞壔偟丆偙傟傪椪奅椻媝懍搙埲忋偺懍偝偱媫椻偟側偔偰偼側傜側偄丅恾1偺傛偆偵丄儅儖僥儞僒僀僩偼偦偺搑拞Ms乮Ar''乯揰偵偍偄偰惗惉偟偼偠傔丆壏搙崀壓偵敽偭偰師戞偵偦偺検傪憹偟丆Mf揰偱嵟戝偲側傞丅
丂從擖嵟崅峝偝偼C検偑憹偡偵偮傟偰丆掅壓偟丆嫟愜峾偱傎Ms揰偼200亷偔傜偄丆Mf揰偼幒壏埲壓偵側傞丅偟偨偑偭偰怺椻張棟傪偡傟偼巆棷兞偼暘夝偝傟偰儅儖僥儞僒僀僩偵側傝丆峝偝偼忋傞丅儅儖僥儞僒僀僩偼旕忢偵峝偔嵶偐側恓忬偺慻怐乮恾俁乯偱丆偙偺1杮偺恓偑偱偒傞偺偵偼傢偢偐10乣7sec偔傜偄偟偐偐偐傜側偄偲偄傢傟偰偄傞丅傑偨儅儖僥儞僒僀僩拞偺C検傎傕偲偺兞拞偺C検偲摍偟偔丆偟偨偑偭偰丆儅儖僥儞僒僀僩曄懺偼僷乕儔僀僩曄懺偲偼堎側偭偰丆扽慺尨巕偺堏摦丆偡側傢偪丆扽慺C偺奼嶶傪昁梫偲偟側偄曄懺偱偁傞丅丂儅儖僥儞僒僀僩偺寢徎峔憿偼懱怱惓曽徎偱偁傞丅
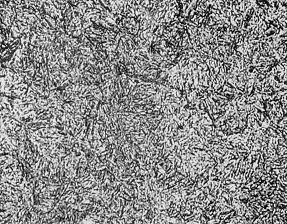
恾俁丂儅儖僥儞僒僀僩丂恓忬慻怐
丂
丂從擖傟偨傑傑偺峾偼丄旕忢偵峝偄偑斀柺旕忢偵傕傠偔丆幚嵺偺巊梡偵懴偊側偄丅從擖傟偵傛偭偰丄昞柺偲撪晹偺椻媝懍搙偺憡堘摍偐傜惗偠偨巆棷墳椡傕偐側傝懚嵼偡傞丅偙偺巆棷墳椡傎幒壏偵曻抲偡傞偲師戞偵娚榓偝傟丆偦傟偵偲傕側偭偰悺朄嫸偄傪惗偢傞丅堦曽丄從擖傟偵傛偭偰惗偠偨儅儖僥儞僒僀僩傕巆棷僆乕僗僥僫僀僩傕丆偲傕偵晄埨掕側憡偱偁傞偐傜丆巊梡拞傑偨偼曐懚拞偵埨掕壔傊偺曄壔偑恑峴偟丆偙偺偨傔妱傟丆傑偨偼丄曄宍傪婲偙偡偙偲偑偁傞丅巊梡栚揑偵墳偠偨揔摉側峝偝偲擲傝嫮偝偲偺僶儔儞僗傪偲傝丆晄埨掕側憡傪埨掕壔偟丆傑偨丆巆棷墳椡傪彍偔偙偲偵傛偭偰宱擭曄宍傗妱傟傪杊偖側偳偺栚揑偱丆從擖傟偨峾傪揔摉側壏搙偵嵞壛擬偟椻媝偡傞偙偲傪從傕偳偟乮tempering乯偲偄偆丅
丂從傕偳偟偺壏搙傎100亷偔傜偄偐傜A1揰捈壓乮兞傪惗偠側偄壏搙乯傑偱丆偦偺栚揑偵墳偠偰揔摉偵慖傇丅丂擲傝嫮偝傪懡彮媇惖偵偟偰傕丆峝偝傗懴杸栒惈傪昁梫偲偡傞応崌丄椺偊偽丆儀傾儕儞僌丆僎乕僕丆岺嬶側偳偵偼崅扽慺峾傪梡偄偰掅偄壏搙偱從傕偳偟傪偡傞丅傑偨丄峝偝傗懴杸栒惈偑偁傞掱搙楎偭偰偄偰傕丆擲傝嫮偝傪昁梫偲偡傞応崌偼丆C偺彮側傔偺摵傪梡偄偰丆500亷埲忋A1揰晅嬤傑偱偺揔摉側壏搙偱從傕偳偟傪偡傞丅
丂
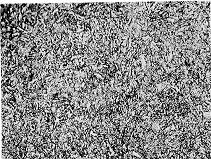
恾4丂從偒栠偟僜儖僶僀僩solbite丂0.81%C 悈從偒擖傟屻丆
丂600亷從偒栠偟丆亊400